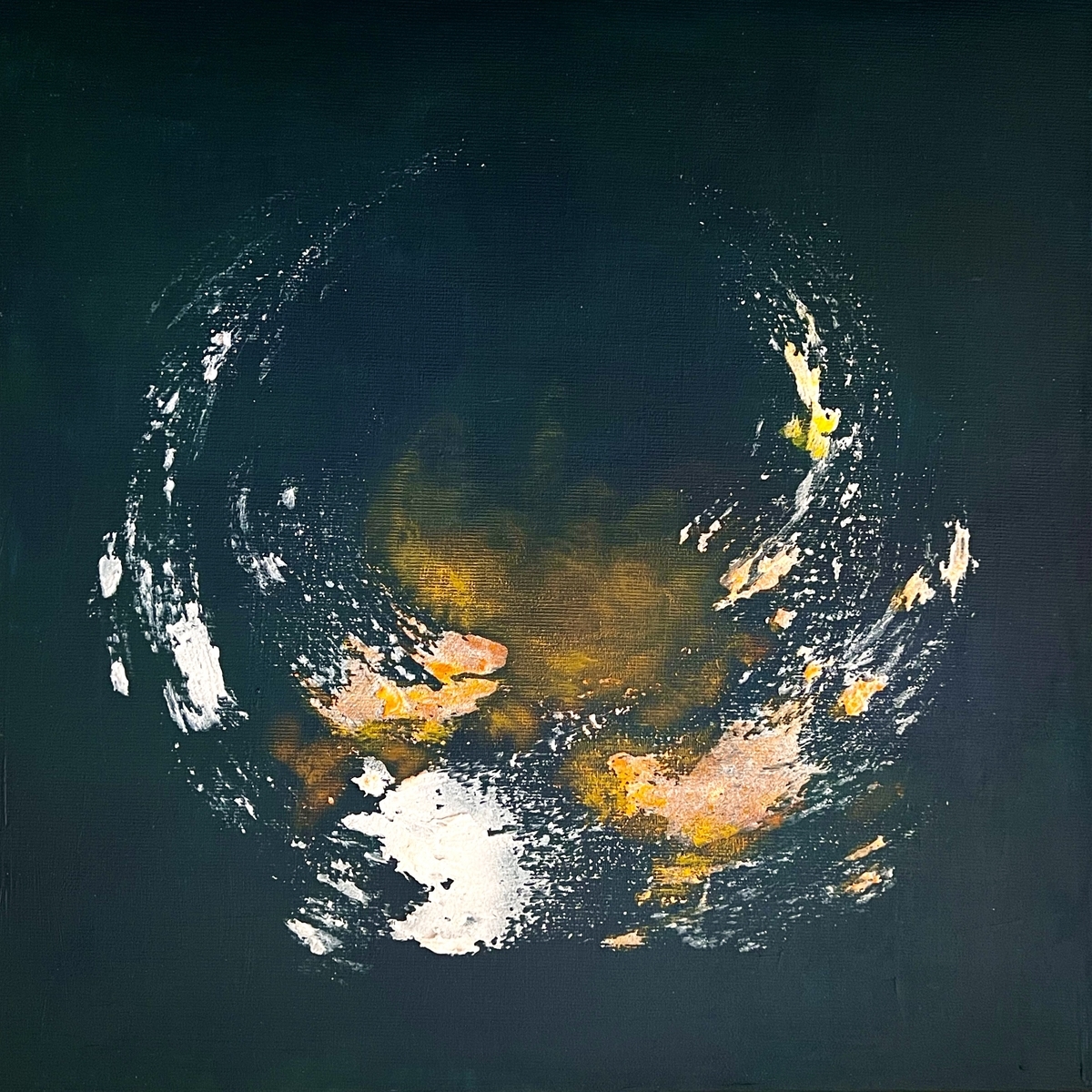バスの中から撮った成田の町
しばらく日本で忙しくしていて、ブログもご無沙汰してしまった。やっと少し書く時間ができたので、帰りの便で観た映画について思いを巡らしてみた。少し前にスイスでも映画「ナポレオン」が公開されていた。ナポレオンには好感を持っていない。それで特に興味も湧かず観に行かなかった。でも、飛行機の映画プログラムにあるので、どんな映画かとちょっと覗いてみた。うーん、やはりどうしてもあの人物には好感を持てない。思い込みの強い野心家で、どんなにたくさんの若者たちが彼の遠征によって命を落としたことか。挙げ句の果ては、自ら皇帝にまでなって。映画は、ジョセフィーヌとの愛憎に重点を置いているらしい。らしい、というのは、隣の人が席を立つ時は中断されるし、時にウツラウツラともしてしまう。まあ、私にとっては集中して観るほど面白くもなかったということか。ただ、この映画を観ていると、どうしても人間の業が引き起こす戦争というものを考えてしまう。人は勇ましい英雄の話を好むようだ。しかし、英雄にはナルシストが多い。ナルシストというよりサイコパス的な人間かもしれない。それにしても、この一人の人間を描くためにずいぶんな制作費を費やしたことだろう。壮大なシーンの多い映画だったが、デビット・リーン監督の「アラビアのロレンス」や、リーン監督の大作にあったような映画の魅力は乏しかった。あくまでも主観的な感想ではあるが。ただ、ちょうど3年ほど前の今頃に書いたブログでの思いを再確認した気がする。そんなわけで、以下、昔のエッセイをもう一度取り出してみた。
***********************************************************************************
今年はナポレオン・ボナパルトが没してから200年だという。1821年の5月5日に亡くなったということから、その頃テレビなどで盛んに取り上げられていた。ナポレオンと言えば、誰しも英雄という言葉を思い浮かべるだろう。彼は、フランス革命後のヨーロッパの歴史に大きな影響を与えた人物で、その功績も大きい。たとえば、ベートーヴェンは彼を称えて「英雄」という曲を作った。けれども曲が完成してから間もなく、ナポレオンが皇帝に即位したと聞いて、「彼も俗物に過ぎなかったか」とナポレオンへの献辞が書かれた表紙を破り捨てたという逸話があるらしい。
ナポレオンは軍人である。戦争に次ぐ戦争の人生だった。理念はあったのだろう。ナポレオン戦争によって、フランス革命の「自由・平等・博愛」の精神がヨーロッパに広がったと言われ、その功績を讃える声は大きい。ただ、その陰で死んでいった数かぎりない兵士のことを考えると、何だかなあと思ってしまう。権力欲も随分と強い人物だったことは明らかだ。自分が皇帝になって、その位を世襲制にしたことを考えても、「自由・平等・博愛」の精神は?と思ってしまう。歴史上の有名な人物を見ると、その権力欲には驚嘆する。歴史の表舞台は、ほぼ戦いに彩られている。古代で言えば、マケドニアのアレクサンダー大王だってそう。日本では、織田信長もそう。英雄って何だろう。学校で習う歴史では、有名な人物の名前を暗記させられた。たいていは、争いの歴史。
一方、歴史に名を残すこともなく、英雄的行為をして死んでいった人たちも数知れない。例えば、これは小説の話だが、カミュの「ぺスト」の主人公の医師リウーや、彼と共にペストと闘ったタルー。彼らは、自分の住んでいる町に襲いかかった不条理に立ち向かう。私は、こういった人たちをこそ「英雄」と呼びたい。こういう英雄たちは、今もこの現実社会にいて、不条理に屈しそうになりながらも日々闘っているのだと思う。今のコロナの状況下の医療従事者たちもそうだろう。「地上の星」という歌がある。中島みゆきの歌だ。この歌が好きだ。他の人のために黙々と仕事をしている人たち。エッセンシャルワーカーの人たちのことも思う。こういう人たちがいなければ社会は機能しない。
そういえば、「英雄」を作曲したベートーヴェンは、去年が生誕250年だった。ここスイスでも、各地で大々的なコンサートが予定されていたのだが、コロナで軒並み中止になってしまった。ベートーヴェンは偉大な作曲家だったが、苦難の人生を歩んだ。コロナ禍でお祝いも縮小されてお気の毒だ。けれども、彼が作った素晴らしい曲は、後の人々の胸に勇気と希望を与え続けている。「第九」で知られる交響曲中の「喜びの歌」は友愛で繋がる理想の世界を歌っているという。日本では、年末の年中行事になっている。新しい年への希望を込めて。戦争という破壊ではなくて、人々が共に平和に生きようという理想を持って歩んでいくために。当初はナポレオンを称えて「英雄」を作ったベートーヴェンは、自らの人生をもって、本当の英雄の姿を示したと言えるかもしれない。